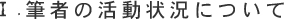トリチウムの放射能の反動と空間理論からの説明 補足 9月12日
モロッコ地震の記事書きが一段落したので、イラストを載せて全体を見直したところです。ついでに気にしていた「トリチウムの放射能の反動と空間理論からの説明」の記事にもイラストを描いた方が良いのかを検討していました。元々素粒子の専門家向けなので今の説明でも十分だと考えていたのですが、こちらの検討内容に一部で抜けがある事に気づけたので、この記事で追加修正をします。前記事はそのままに、何を間違えていたのかを明確にする部分も、素粒子の学者さん達には分かりやすいでしょう。
一般の方向けでは難しいままで恐縮ですが、β崩壊の理論がグルーオンの安定度という、原子核の理論を抜きにして語れない部分と、空間理論におけるニュートリノとZボゾンの電荷の対応を描くことになります。ニュートリノにごく微小の電荷を生み出す仕組みとは、Zボゾンの持つごく微小の電荷に対応していると明らかにする話です。
現代素粒子論によるトリチウムのβ崩壊の理論は1930年代の物であり、現在のクオーク理論にも対応出来ておらず、古い時代の量子力学の拡大解釈が残っているので、様々な原子核の持つ、様々な結合エネルギーの違いを適切に処理する部分は全く描けていないのでした。この問題を解決できる仕組みを提供していたつもりだったのですが、もう一歩踏み込める部分がある事に気付けてこの記事です。
結論は簡単です。
βとγの崩壊について
1)グルーオンのない真空中で、何らかのエネルギーにより量子対生成を起こすと、そこではW+とW-の寄与により、e+とe-が対生成される。
2)元核の電荷が変動するβ崩壊において、グルーオンによりW+とW-の寄与から、e+とe-が対生成されるだけでなく、Z+とZ-の寄与により、ν+とν-が対生成される。e+はdに取り込まれuになるが、同時にν+も取り込まれるかは現時点では不明瞭。相互作用の低さの面からは飛び出せるし、取り込まれることにも可能性を感じる。
尚、e+はdに取り込まれuになると言う表現は、電子捕獲の電荷が逆の物としてクオークとの融合に実績があると前記事でも書くべきだった。
3)元核の電荷が変動しないγ崩壊において、グルーオンによりW+とW-の寄与から、e+とe-が対生成されて対消滅するが、この時にはZ+とZ-の関与はなく、νは発生しない。対消滅の一方からγ線が出力される。
4)エネルギーの辻褄合わせに、Wを使わないZ+とZ-の対生成単独での利用により、ν+とν-が対生成される可能性があるが、加速器実験下で再現出来ても、自然にはおきにくい反応と思われる。エネルギーの大きさとしてWに従属する感じを受ける。
5)以下の電荷1単位の大きさが不明瞭なままです。
真空から生成される電荷=グルーオンから生成される電荷+νのごく微小な電荷
真空から生成される電荷=グルーオンから生成される電荷
この疑問には空間理論の進展が答えるでしょう。
ニュートリノの相互作用について
a)ν+はe-やd-などの負電荷を持つ粒子と相互作用できて、そのエネルギーを電荷の大きな側に渡して、自身は負電荷と釣り合う部分で電荷ゼロになって空間に帰る。電荷が逆でも同様になる。νは消滅する。荷電カレント相互作用に相当すると考える。Z+とZ-の関与と考える。
b)同じ電荷の場合は電荷の反発で衝突できないはずなので、弾性散乱のみが起きて、条件に応じた運動量の交換が起きる。νは消滅しない。中性カレント相互作用に相当すると考える。
現在の素粒子論では、W+とW-とZ0が存在するだけです。ここでW+とW-を電荷が1/3~1に相当する量子対生成の仕組みだとすると、弱い力としてのZ0の存在目的が不明瞭になるのです。
空間理論としてはZは電荷ゼロではなくてごく微小の正負を持つはずなので、これがどの様に作用しているのかを考えたのでした。結果はグルーオンがあると登場できて、核反応の前後で電荷が変動することが条件で、そのごく微小な電荷を操作できるのでしょう。こう考えるだけで辻褄が合うのでした。
いわゆる標準理論にとっては、ごく微小な電荷など存在しないと同等なので、今の理論体系が成り立つのでした。よく考えられている物でもあり、核のエネルギーバランスを、グルーオンを通して保つ仕組みなのでした。
γ崩壊の場合、グルーオンのエネルギー準位のような物があって、この遷移に応じてγ線が出て来るというのが今の原子核側の解説ですが、これだとグルーオンからガンマー線が出てくることになり、一つやっかいな問題を残すのでした。グルーオンには光にはないカラーなどの特性があるので、これをゼロにする仕組みが必要なのでした。ただ切り出せば良いという乱暴な議論では先に進めないのです。依り代にエネルギーを渡して新しい性質を付与する方が簡単なのでこの解説です。
まずはこれだけでも空間理論的には素粒子論とグルーオンの安定度という原子核の理論に矛盾なく放射性崩壊を説明出来るでしょう。空間理論も空間理論から生み出されている核理論もまだ未完成ですが、自然現象を説明出来るという部分はこれからも広がりそうです。
これはイラストに描くと分かりやすいので、ジェド柱霊界ラジオと質量制御の機器開発がニュースになれたあとで作業を実施します。必要に応じて、続きの解説も書くかも知れません。
続きの難しい部分を抜きにしてここまででも、素粒子と原子核の専門家には簡単に理解出来るでしょう。
この続きは、コペンハーゲン解釈がもたらしている量子力学の拡大解釈の問題点の解説です。素粒子論はそこにありもしないエネルギーを量子ゆらぎの範囲で利用できると物理的根拠が非常に薄弱なままに、非常に大きなエネルギーを真空銀行から借りられると考えています。ここにある矛盾を説明したいと思います。
まずは理解しやすい、量子力学には隠された変数があるという議論です。比較するのは一般相対性理論と空間理論の関係です。同様に量子力学と空間理論の関係性を考えて欲しいのでした。
空間理論からは、一般相対性理論が素粒子論における近似式でしかない部分を明確にしています。光速度で無限大になる質量などは、素粒子論側からは出てこないのです。素粒子論こそこの世界の微細な現実を表すのであり、ここに一般相対性理論の限界が表れていて、現実の姿を現せないのでした。一般相対性理論は現実に対する近似式でしかなかったのでした。現実の姿を記述する基本式ではないのです。
私達は近似式でしかない物を、この世界を現す基本的な物理式だと誤解してきたのでした。この意味でもブラックホールや重力波天文学など、現実を無視した上に成り立つフェイクであり、幻なのでした。にもかかわらずノーベル物理学賞であり、ますます現実無視が私達には板に付いているのでした。
空間理論の立場からは、量子力学も同様に近似式でしかない部分を推定できるのです。この続きこそ重要な議論なのでした。
まずは、量子論を暴走させているコペンハーゲン解釈の問題点です。彼らは確率の議論しかしていないのに、いつのまにか、確率ではない議論をそこに混ぜ込んで物理計測における混乱を促しているのでした。
以下コペンハーゲン解釈における、定式化です。wikiより切り出します。
ノイマンが1932年に行った定式化は
・量子系と観測者(観測装置)を分離する。2つの境界はどこに引いてもいい。
・量子系の状態は、観測していないときはシュレディンガー方程式に従う
・観測により波動関数が収縮して、1つの測定値が得られる
・どの測定値が得られるかは確率的であり、ボルンの規則に従う
というものである。ノイマンの定式化は現代でも通用する。
ここにある分かりやすいインチキの構図は、「観測により波動関数が収縮して、1つの測定値が得られる」という部分です。こちらの物理的客観性の立場で表現するなら、計測により波動関数が収縮する事はなく、複数回の計測により「統計的に結果を収束させる」ことで、得られる物こそここに書かれた1つの測定値であるとなります。
「観測は波動関数を擾乱するでしょうが、収束などしないでしょう。」波動関数か収束するというこの表現はこちらにとってはあからさまなインチキです。この統計処理こそコペンハーゲン解釈の根底にある、数学統計的な結果でしかない物を、統計処理から解き放って1つの物理の現象解釈にすり替える部分です。平均値と1回の計測が一致するなど偶然でしかなく、ここにある差を意識できなくて統計的計測結果を語るななのでした。
極端に書くと、擾乱された波動関数に隠された変数が含まれていても、統計処理される波動関数に隠された変数が顔を出すかは確かめる必要があると言う事です。「どの測定値が得られるかは確率的であり、ボルンの規則に従う」という部分は単なる数学的な決めつけなのでした。
こちらの立場は今は否定されているアインシュタインの隠された変数に近いのであり、以下の解説が得られるのでした。
EPRパラドックスが発表された当時は、アインシュタインらは局所実在論の立場を取っていたため、量子論が実在論的に完全でない結果を与えることを「パラドックス」であるとした。
現在では以下の続きがあるのでした。
局所実在性を満たす理論について、ベルの不等式が成立することが知られている。ベル不等式の破れの検証(フリードマン, クラウザー:1972年、アスペ:1982年など)により、ベル不等式の破れが実験的に確認されている。 そのため、局所実在論は成立しないと考えられている。
ここには、「局所実在性を満たす理論について、ベルの不等式が成立することが知られている」とされているのですが、ベルの不等式が常に正しいのかなどは、証明されていない問題だと言えるでしょう。ここは数学的になるでしょうが、どこで理論が破綻しているのかなどは、1つの論理式では計れると決まっていないでしょう。この例こそ一般相対性理論と空間理論の差になるからです。結果が出るまで普通に分からないし、予測も出来ないでしょう。
続きが真空銀行の登場している解釈の問題です。まずは不確定性原理の存在で、エネルギーと時間の積が、一定の大きさを超えないという現実です。これは「計測においては」その仕組みの一部として認められるでしょうが、現実にそのままに、エネルギーが時間との積で変わり得るでしょうかという問題です。
計測時には計測手法の問題もあって、長い時間がかかるなら、エネルギーはそこに分散するので低くなるでしょうし、時間との積で得られても現実的でしょう。しかしながら現実の現象において、時間を積分してエネルギーを溜め込むというあり方には、どこに現実味があるのでしょうか。ここでの疑問はその仕組みを説明しろであり、そんな物など存在しないのでした。不確定性原理が計測における原理であると言う部分が、抜けていると思えてならないのでした。
この場合に起きる事など簡単であり、その場にあるエネルギーを積分する手段がなければ、不確定性原理を利用してエネルギーの最大値を求めるあり方などなり立つ理由があってたまるかという現実です。ここにある物こそ馬鹿げたコペンハーゲンというか不確定性原理の暴走なのでした。ここでは理由なく波動関数は収束しないと書くのでした。時間積分も体積積分も出来るなら、方程式を書いてやって見せろなのです。1930年代からもうすぐ100年ですが、いい加減間違いに気づく時でしょう。
仮に時間で積分できるとしても、その分その現象が起こりにくくなるのであり、β崩壊が現実の確率的な現象として表現できるでしょうかとなるのでした。ここは計算していないので流すのですが、エリアに存在するエネルギーを集めるなら面積や体積で積分するのであって時間で積分する意味が薄いのでした。何よりも、どうやって積分するのかという議論に答えがないのであり、意味などないに等しい議論なのです。
ここまで進んできた空間理論としては、馬鹿げた真空銀行という無限責任の貸し手は存在できないのです。その仕組みを普通に自然科学として実現できないからです。自然としては空間理論に従い真空に充満している電子と陽電子の前駆体のエネルギー揺らぎしかないでしょう。それほど大きな物にはならないと思います。
この記事で解説したように、β崩壊に際して必要なエネルギーなど、当該元原子核のグルーオンが持つ範囲です。このグルーオンが安定度の上昇を求めて起こす変化こそβ崩壊であり、エネルギーを真空銀行から借りなくても自前で処理できるのでした。この意味こそ理論不明な不確定性原理における積分作用を必要としないという意味です。
WボゾンもZボゾンも、弱い力を表現するための物であって、その仕組みは空間要素側に実装されている物であって、絡みつく正負の電荷を操作できれば良いのでした。
素粒子論の言う所のWボゾンとZボゾンは、それが作用している場に相応するエネルギーを投入すると、そのエネルギーを代表できるので粒子化してくると言う仕組みでしょう。量子対生成の粒子にもなれるのですが、普段は必要なエリアで絡みつく正負の電荷を操作できれば良いのでした。大きなエネルギーが常に必要だと、この種の素粒子変化が成り立たないのでした。
間違っても波動関数は、エネルギーを積分してこの作用が可能な形に、収束することなどないでしょう。自分の都合丸出しに自然が動くことなどないのでした。こちらの解説として、WとZのボゾンが存在できる場として関与は出来るでしょうが、動かすエネルギーはeとνのばらつきの範囲であって、WとZのボゾンの大きさなど必要ないでしょう。
あとは素粒子論としても、WとZのボゾン抜きで、現実を現せるファインマンの遷移図を専門家達が合意の元に描いて欲しいと思います。
量子テレポートに到っては、光の場合ですが、インチキその物でありノーベル物理学賞の間違いとして批判してあります。以下の記事を参照下さい。
ノーベル物理学と生理学賞の間違いと科学界のバレないつもりの嘘1~3
http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=2031
DB_ID@=2031~2033がこれらのアドレスです。
物理量の変化としてはビームスプリッターという部品を通過した時点で確定しており、読み出しを待つだけのトランプマジックです。これを支えている間違いは、1つが「・観測により波動関数が収縮して、1つの測定値が得られる」という嘘で、これはその物理現象に依存する物です。ここでは読まないと確定しないが嘘なのでした。
もう一つは如何にもそれっぽい不思議な実験結果が3つくらい出されているのですが、どれも自分自身に自分自身をぶつけるというインチキです。光の大きさを無視して不思議なことが起きているというのですが、方程式だけ見ていて現実を見ていないので勘違いをするのでした。こういったあり方こそコペンハーゲンの黙って計算しろという傲慢な姿の先にある物なのでした。私達はコペンハーゲン解釈の中にある問題に向き合う時だと言う事です。アインシュタインに先見性があったのでしょう。
微小な電荷と電荷1に分けるアイデアという、この概念はヒッグス粒子にも拡張できるのですが、続きは難しいでしょう。ごく微小な電荷で非常に大きな質量ですので、電荷1では簡単に加速器では作れない馬鹿げたと書けるほどのエネルギーを持てるのかも知れません。用途次第ですが、現状では使い道がないので空想上の素粒子になるのか、専門家の検討を待つ所でしょう。
稲生雅之
イオン・アルゲイン